ちょっと前までの資料は紙だった
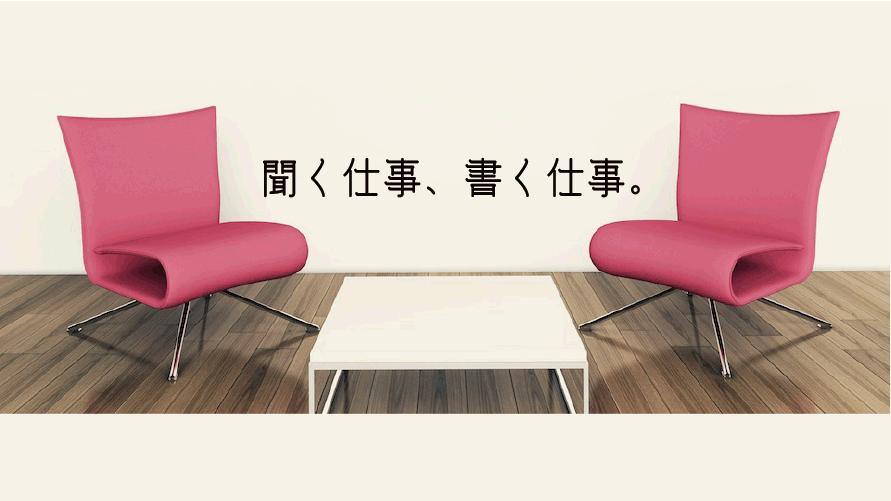
8月は昭和を振り返る番組が増えます。
よくNHKのドキュメンタリーや特集を見ますが、そのときに出てくるのは「紙」の資料なんですよね。それも、縦罫が入った原稿用紙に万年筆でしたためた、その人の息づかいまでが聞こえてきそうな字で。
「紙」の資料ということは、同じ紙の前で必ず誰かが、何かを考えながらペンを走らせたということ。その「紙」を前にすると、時間は違えども書いた人と同じ空間を共有します。
昔の資料が出てくる映像を見ながらふとそこに気がついたとき、翻って今の自分を考えてしまいました。
この記事もキーボードを打ちながら「書いて」います。文章の善し悪しを考えるときも画面上の字を見ながらだし、人に書き方を伝えるときも前提は「打って書く」。ペンを持っている人に向けての話をしていないし、考えてもいない。
このブログを読んでいる方も、私の直筆文字はほとんど見たことがないですよね。でも知らなくてもどうにかなってしまう。文字は「情報」になってどこにでも飛んでいきます。
本来なら、書くことと読むことは「紙」が介在していました。読み書きは、手触りがあったり、ページをめくったり、ちょっと字を書き間違えたり、インクの出に悩んだり、バランスを見たり、いろんなことを気にしながらやる行為でした。
知らないうちにそういう生活から離れているんだなあ。
字を知っていても「書」けない日が来ると怖いので、もうちょっと「紙」を大事にしようと思います。
「聞き方」を動画で学べる!
-
前の記事

プロフィールの書き方と、最適な自分探しの方法 2010.08.14
-
次の記事
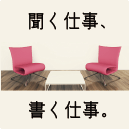
文章を校正する3つのステップ 2010.08.18
