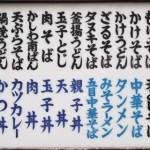人と比べなくなるまで、時間はちょっとかかる。

2010年にフリーになってからいろんな「仕事の仕方」を模索しています。もっとアピールしたほうがいいんじゃないかとか、ツールを使うべきかとか、逆に泰然としていたほうがいいのかとか。ここ半年くらい、何となく「こんな感じでいいのかな」と思えるようになりました。以前よりも人と比べなくなって楽になったというか。
■ 第1の吹っ切れ:じゃあ、料金はちゃんと出しておこう。
フリーになって一番気になったのは「他の同業者はどうしているの??」でした。出版業界にいたわけではなく、編集プロダクションが行う手順もわからない。教えてくれる先輩がいないので自分でどうにかするしかありません。ぼんやり「あの辺に仕事がありそうだ」と思っても近づき方を知らず、最初の1,2年は本当に周囲をグルグル回っていました。
人的なツテがないので、見知らぬ皆さんに「ライター業やってますよ!」と知らしめるべくブログとサイトを立ち上げました。それが後々よかったんですが。
ライターになりかけの頃の試行錯誤は有料noteにもまとめています(たぶん次回が最終回)。
■企業OLがライターになるまで。第4回更新
最初から一貫しているのが一般企業や個人事業主のお客様が多いこと。そして、料金をサイトで明らかにしていること。
これは今でもいろんな意見をいただきます。ライターの大先輩から「そんなことしてたら仕事来ないよ!」と言われたこともあります。東京の出版社や編プロは案件ごとに条件が変わるものなので、最初から「この料金を払ってもらえないなら受けません」というスタンスは門戸を閉ざしているようなもの。だから「ご相談ください」がよいと教わりました。
「そうなのか…」と迷ったこともありました。1件も来ないなら、自分の考えは間違っているだろうから直さないといけないなとも考えました。
でも世間は広いもので「料金がわかるから頼んだ」というお客さんが企業のほかに編プロや制作会社でもあるんですね。ゼロではなかった。
そういうお客さんは「ここなら料金の目安がわかる」と頼んでくれます。周りのライターほとんどが料金を明らかにしない状態であれば、逆手にとって「明示していますよ!」が売りになると気づきました。
出版界は難しいかもしれないけれど、一般企業を相手にする仕事ならむしろ料金ははっきりしていたほうがいい。これも続けていてわかったことです。交渉するときも物差しがはっきりしているので両方が納得しやすい。
出版社だけがライターを必要としているのではなく、ライターを連想しない業界でも働ける場所があります。じゃあそこへ行けばいい。比べ始めると「あの雑誌で書いているのか」とか「あのサイトの仕事を受けているのか」とキリがなくなります。でも(偶然ですが)最初から違う土俵でで仕事ができているので、それでいいじゃないかと。
「仕事を頼む前からいちいち細かい」と思う場合は、他の違うやり方のライターさんへ頼んでもらったほうがお互いのためになります。その代わり「仕事を頼む前にしっかり確認したい」人だけが来てくれます。
■ 第2の吹っ切れ:自分が好きなところへ設定しちゃえ。
明示する料金はフリーになるときに調べて決めました。正直、高いと言われることもあります。でも時間をかけて仕事と向き合うとき「これくらい報酬がないとモチベーションが保てない」というラインがあります。それはキープしました。
仕事をしていて思うのは、どんな料金でも必ず3パターンの人に出会うこと。「それは高いよ」「だいたいこれくらいでしょう」「えっ、そんな安いの?」という3つです。1時間あたり1000円だろうが、10000円だろうが、30000円だろうが、必ずあります。
人はその人の価値観で意見するので(私もそうですが)、その人にとってぴったりの金額を教えてくれます。でもそれが私にぴったりかどうかは別の話。
■ 第3の吹っ切れ:条件に疑問があると断れるようになった。
このほか、最近はっきりしてきたのが仕事の選び方です。私は見積もりを出して何往復かやり取りをします。その間に相手方も私がどんな書き手なのか、ちゃんと仕事をするのかを見極めます。
このプロセスで自分がぼんやりと「受けたくないな」と考えていたポイントが明確になってきて、実際の行動につながるようになりました。私が「受けたくないな」と思う仕事は以下です。
・最初に金額を言わない
・納期がわからない
・大量にこなさなければいけない案件
・担当者が見積もり確認を面倒くさがる
経験上、九分九厘、上記の案件だと原稿のやり取りでも問題が出てきます。何を伝えたいのかわからないメールが来たり、支払いの条件が出てこなかったり、直しの指示が曖昧だったり。そのために悩んだり気にしたり怒ったりするのは本当に時間が勿体ないので、最初から「受けない」と線を引くようになりました。
実際に受けたとしても、相手からすると「何でこんなに細かいんだ」「何でこんなに高いんだ」「面倒なライターだな」と感じます。タイプが違えば仕方ない。かえって迷惑をかけることになるので、相手のためにも別のライターを探してもらったほうがいいんです。
その代わり、以下のお客さんはお互いに「よかった!」と思いながら仕事を進められます(私の場合は、ですが)。
・ブログやサイトの文章を見て「こういう文体がいい」と思った
・作業前に料金がわかったほうがよい
・限られた予算内で収めたい
・話せるけれど書けない、話すことならたくさんある
書いていて思いましたが、これって当事者じゃないとわからない感覚ですね。だから仲介者のない直接受注のほうが向いているかもしれません。
「そんなやり方じゃこういうお客さんが取れないよ」という意見に悩んだ日がありましたが、違うお客さんがいるとわかったので比べなくなりました。
■ 第4の吹っ切れ:コミュニティの大小を気にしない。
大きなコミュニティを作るかどうかも悩みでした。ビジネスの本を見ると「仲間をたくさん作る」「広げてもらう」「そのためにこんなことをする、ツールを使う」という情報がたくさん載っています。でも私の場合は作らなくてもいい、と割り切りました。
もちろん経験した方が広める口コミはありがたいものです。おかげさまで自分ではつながることができない人へ自分の情報が伝わります。だからといってそのパイプを太くしたり強めたりするために、血眼になる必要はないだろうと。
自分自身が積極的に大人数の中に飛び込むタイプではなく、広めるときは「本当に自分がいいと思った」ものしか広めたくないからでしょうね。おつき合いとか社交辞令で縛られるのがイヤなのです。
できれば自分のサービスについても「こういうメリットがあるから、じゃあ紹介する」と言われるよりも「本当に良いと思ったから」と紹介してもらえるほうが嬉しい。
大きなコミュニティで求心力がある人の真似をしようと思ってもできないし、自分のやり方でチビチビ来たら、やっぱり似たような考え方の皆さんが近くに来てくれるようになりました。じゃあこれでいいじゃないかと。
——————-
上記の4つをフリーになった直後に割り切るのは不可能でした。「うわ、言い過ぎたみたいだ」とか「ああ、言い足りなくて失敗した」というのを何度も経て、世間の振り幅がわかって、その結果で「立ち位置をこの辺にするか」と決められました。さんざん比べたから、比べないですむ位置がわかったというか。
仕事を始めてすぐ割り切っていたら、今以上に鼻持ちならない状態になっていたでしょうね。数年かけてすっきりして、ちょうどよかったです。
下記の記事も参考にどうぞ。
■ 良いライターの探し方、受注・発注それぞれから考える

■ 苦手な項目をメニューに入れない
★人間関係を良くする聞き方セミナー ライターの聞き方をコンパクトに理解
★人間関係がちょっとラクになる「聞き方」の基本 丘村の電子書籍 第2弾
★書き方・聞き方のコツ無料PDF集 のべダウンロード1500突破!
「聞き方」を動画で学べる!
-
前の記事
![[書評]『「読ませる」ための文章センスが身につく本』奥野宣之](https://edi-labo.com/blog/wp-content/uploads/IMG_3789-150x1501.jpg)
[書評]『「読ませる」ための文章センスが身につく本』奥野宣之 2014.11.11
-
次の記事

【第3回 本屋で本を3冊買う会】開催しました! 2014.11.27