取材する側から「される側」になって改めて見えたこと
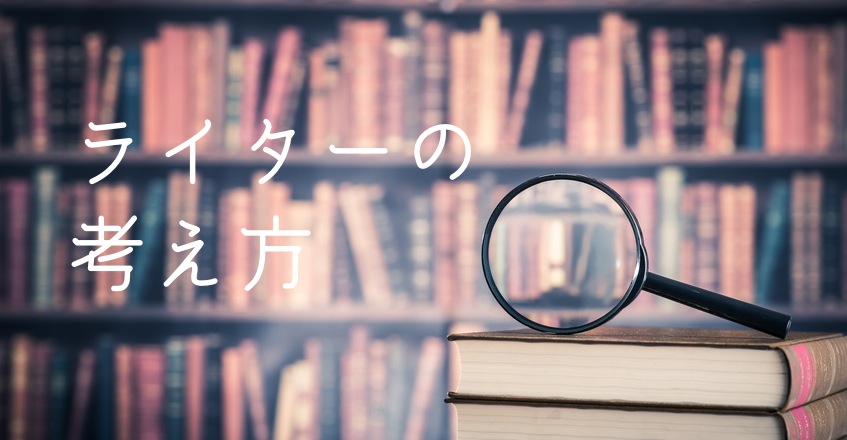
先日、キキゴタエというオウンドメディアから取材依頼をいただき、ほぼ初めて自分について長く話す機会をいただきました。最初は私が取材する仕事の依頼かと思ったら、相手の方がこちらに聞いてくださるというのでびっくり。
記事は無事公開されています。
ライターではない方からの取材だから見えた
キキゴタエはインタビューサイトとして【有名・無名に関わらず、全て私たちの「面白そう・興味がある」という主観】で人物を選定、運営者はビジネスコンサルティングやスモールビジネスを支援しているゲートプラスという企業です。
取材でお会いした方もライター専業というわけではなく、他の業務も兼ねながらインタビュー記事を制作しています。他の記事を読んだとき、あまり加工されず会話がそのまま残されている印象があったので、その点を伺ったところ「テープ起こしスタッフの原稿から一次加工をこちらで行い、あとは取材対象者から自由に手直ししてもらっている」とのこと。
取材依頼時も「自由に直してくださって結構です」とあったので、ライターの仕事としては珍しいスタンスだなと思いました(正直にいうとライターとしてそれはマズいだろうと思いました)。でも本業ではないのだとわかって納得。それなら手直し込みのほうが効率良く、双方が納得した形で原稿が公開できます。
私も一次加工の原稿を受け取ったあと、かなり文章に手を入れさせていただきました。このプロセスだからわかったことがいくつかあります。
「言葉のあや」の危うさとチェックの必要性
私が取材する側のときは、話し手が勢いで語った言葉やネガティブな言い回し、批判や悪口などは書き言葉にしません。それは話し手の本意ではなく文字にしてもメリットがないからです。新聞や雑誌などジャーナリスティックな取材なら言葉尻や語彙から攻撃的な構成もありですが、相手の依頼で書く文章ではそれをしません。
今回取材をされる側になったとき、上記の心配があったので当日の会話ではなるべく強い言葉やネガティブな話はしないように心がけました。が、やっぱり興が乗ってくると口が滑ってしまいます。一次加工の原稿ではその言葉が思いっきり残っていて慌てて削除しました。
このインタビューでは最終形まで自分で確認できたのでよかったのですが、そのまま抽出されて掲載されてしまう場合は怖い。世の著名人はその網をくぐるような言い回しで、なおかつキャッチーで使える言葉を瞬時に選ぶ仕事をしています。それだけで尊敬です。
また、制作側もスルーしてしまうと予想外のダメージが出ます。先日も大手下着メーカーの社員が「東北美人に抱かれているような下着」と語った言葉がそのまま載って非難を浴びました。本意はもう少し違ったかもしれない。その場の盛り上がりのために口が滑ったかもしれない。逆に本心でそういったかもしれない。どちらにしろ制作チェック時にカットできたはずなのに公開してしまった。作り手として身につまされる話でした。
話したときの言葉と、文字に変換した言葉とは違う。その場で消費されるための言葉と残すための言葉、それぞれ果たす役割も違います。ライターとしては差異をちゃんと使い分けなければ、と意識を新たにしました。
頑張ってファシリテーションしなくていい
もう一つ「取材される側」で発見したのは、それほど取材側がファシリテーションしなくても場が進んでいくという点です。
私はこれまで、どちらかというと取材の軌道を意識して「外れないように」と考えながら聞くタイプでした。もちろんそれは必要なのですが、ケースによっては「そんなに質問しなくてもいい」「意見を絞りすぎているのでは」と指摘されたこともあります。
今回の取材は、最初に箇条書きで「こんな方向で」とは言われたものの、全般に話し手が自由に放置されている雰囲気。ただ目の前の箇条書きがあるのでやっぱり「外れないように」という意識がこちらに出てきて、気づくとそれなりの量を話していました。
テープ起こし後の一次原稿を見ると、だいたい当日の順番通りに話したことがほぼそのまま書かれています。でも大きく破綻しているわけではなく原稿として成り立っている。手直しでも構成はまったく変えずにすみました。
このプロセスの第一印象は「こういう方法でも原稿ができるんだな」。特にボリュームを必要とする原稿は相手の言葉量が命です。実は取材時は「もっと取材側で誘導したりしないのかな」と感じていました。でも結果を見ると形になっています。今まで他メディアの長文記事ついて作り方がピンと来ていなかったのですが、今回やっとわかりました。
8000字近くの記事と、別の反省点
取材は1時間ほど、手直しのときに多少書き足したフレーズ込みで8000字近くの記事として公開されました。
悔やまれるのは(今さらどうしようもないのですが)写真写りの悪さです。通常は2名取材で聞き手とは別にカメラ係の方がいるそうなのですが、今回は1名取材。話が終わってから改めて写真を撮りました。これがまた大変。元のレベルが低いのにポーズも笑顔も下手くそ(笑) 使えるショットが少なかったと聞いて非常に申し訳ないと思いました。
せめて笑顔とか。せめて化粧をもっとうまくするとか。言葉とは違うところで大きな反省です。
でも内容は自信ありです! 丘村の「聞き方」と新刊の「ビジネス書 実用書の書き方」を話題にしていただき、おかげさまで楽しくお話ができました。皆さんのお仕事のお役に立てれば幸いです。
「聞き方」を動画で学べる!
-
前の記事
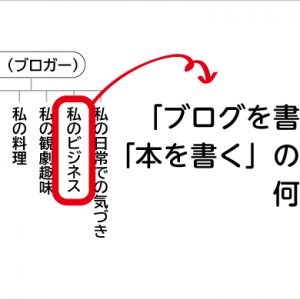
「ブログを書く」と「本を書く」はどう違うのか 2018.06.10
-
次の記事

パワーショベルを動かせる人になる。車両系建設機械(整地等)技能講習の体験記をまとめました。 2018.08.03
