『スクリプトドクターの脚本教室・初級篇』を読みました

脚本や小説を書くことに興味はあるものの、自分の仕事とはずいぶん離れています。仕事で行うライティングでは人から情報をいただいて整理整頓するのに対して、フィクション作家は世界観や感情をゼロから生み出して構築する。どう生み出して組み上げるのか、よくわかっていないけれど知りたい。そこで、この本を買ってみました。
自分にある「殻」と「ブレーキ」をどう扱うか
著者の三宅隆太さんは脚本家・監督の経験を持つ「スクリプトドクター」。行き詰まった脚本の悪いところを見つけて「治療」する人です。現場にそんな職業があるとは失礼ながらまったく知りませんでした。
本の前半では行き詰まりやすい脚本の考え方のクセと修正方法、後半ではスクリプトドクターの詳しい仕事内容が書かれています。
脚本や短編の創作はやってみたことがあります。でもまさに指摘されているような「窓辺系」のストーリーで人が動かないんですよ。自分が手の届く範囲でしか人が動かない。動かさないといけないとわかっているけれど、動かし方がわからない。動かしてもいいけど、突拍子がなくて筋がつながらない。
どうすればいいんでしょう、と言っても「それを考えるのが作者の仕事」です。悶々と考えるだけでずっと袋小路でした。
木村さんは話の筋に触る前に、思考のクセについて解説します。キーワードは「殻」「ブレーキ」です。実際の例を紹介しながら、どう突破したか、何に注目したか、何に縛られていたかを書いています。
読みながらうっすら見えてきたのは、私はたぶん人を追い込むことを良しとしないし、そうしたくないし、されたくないと考えている事実です。
言い換えると「人に意地悪をされたくない」と同時に「意地悪をしたくない=意地悪をする人と思われたくない」。日常生活でならいいのですが、これは物語を作る上では非常に邪魔な感覚のようです。なぜなら主人公をピンチに陥れたり、性格が悪い人物を(魅力の有無はさておき)登場させたりできないからです。
だから話が動かないし、人も動かないし、波もない。なるほどなあ。木村さんがいういわゆる「窓辺系」で、内面をウロウロするだけの話になってしまう。物語と自分を良い距離感で切り離せないんでしょうね。まずこの「殻」を破らなければいけない。
木村さんは「殻」を破った後にストーリーを貫くべき「話の軌道」について解説しています。この軌道の抜き出し方はロジカルで、丁寧に辿ればおそらく誰でも理解できます。
木村さんは小学生の頃から何千本の映画を観ながら好きでそれをやっていて、量の蓄積が半端ないです。だからこの仕事で実績を上げられている。本には長年培った方法論が惜しみなく披露されています。詳しすぎたのでこの厚さ、価格になったことは中にも書かれていました。
スクリプトドクターの仕事とは何か
後半はスクリプトドクターの仕事について。
感覚に頼らず構造を見抜き、必要な手当を適切な形で提案し、直していく。脚本自体の構造の分析のほかプロジェクトの人間関係の構造まで配慮して、停滞したコミュニケーションが動き出す提案方法を選ぶ。幾重にも気配りが必要な難しい作業なんですね。
全体を通して印象的だったのは、木村さんが徹底的に書き手の味方であること。事例では脚本講座の生徒さん、プロジェクト内の脚本家さん。そして良い書き手であろうとする、読者の味方でもあります。
すべてを読み終えた後に続く「おわりに」は、自信をなくしかけた書き手に響く言葉がいっぱいです。もし「自分は書き手としてダメダメだ」と悲観してしまったら、開いてみてください。言葉が漢方のように効いてくるのではないでしょうか。

中級編も買いました! これから読みます。

★人間関係を良くする聞き方セミナー 2016/10/22に開催、ライターの聞き技
★書き方・聞き方のコツ無料PDF集 のべダウンロード2000突破!
「聞き方」を動画で学べる!
-
前の記事

共通点を探さない会話術、体験できます【聞き方セミナーのご案内】 2016.09.01
-
次の記事
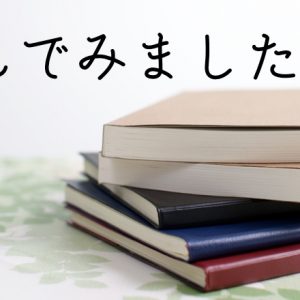
『本当はひどかった昔の日本』大塚ひかり著 を読む 2016.10.01


